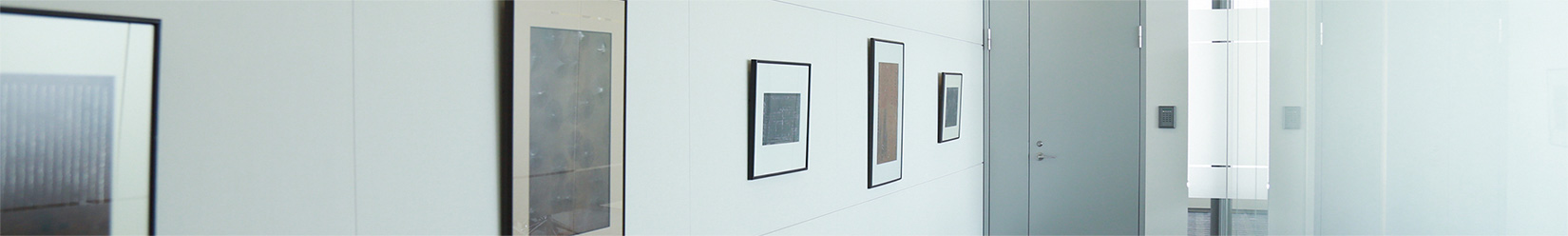
国内商標
HOME >
国内商標 > 特許庁への手続き
特許庁への手続き
出願から登録までの流れ
出願すると、特許庁の審査官が出願内容を審査し、登録できるか否かが決まります。

1出願手続
出願の際に必要なものは下記の通りです。
- 商標 (文字商標・図形商標などがあります)
- 指定商品/役務 (願書には、その商標を何に使用するかを記載しなければなりません)
- 出願人の情報 (氏名又は名称, 住所)
「どの商標を出願したらよいか」、「どの商品について出願したら良いか」は一番重要なポイントです。
じっくりお話しを伺いながら、「貴社のブランドを守る最善の方法」を提案いたします。
2中間手続
審査され、登録要件を充たしていないと判断された出願は「拒絶理由通知」が発せられます。
「拒絶理由」の内容によりますが、下記の応答書を提出することで、拒絶理由を解消し登録できる場合があります。
- 手続補正書の提出
- 意見書の提出
- 上申書の提出
- その他審査官が要求する書面の提出
また、審判請求や交渉などにより、拒絶理由を解消できる場合があります。
必ずしも、「拒絶理由通知」=「登録できない」ではありません。
「拒絶理由通知」の内容をプロの視点で検討し、可能であれば複数の対応案を提示した上で、最適な方法はどれなのかを一緒に考えてまいります。
ご自身で出願した商標登録出願が「拒絶理由通知」を受けて困っている方の相談にも応じますので、お気軽にご相談ください。
3登録手続
いよいよ登録手続です。特許庁から「登録査定」が届いたら、それは「審査に合格しました」というお知らせです。出願人が登録料を納付すれば、そのまま設定登録されます。
登録料は、「10年分を一括で納付する方法」と、「5年ごとに分納する方法」があり、どちらにするかを出願人が選べます。
貴社の商標は設定登録されました。あなただけが、その登録商標を日本全国で使用でき、他人にライセンスすることもできます。
4更新手続
登録手続によって設定された商標権の存続期間の満了が近づいても更新手続により権利期間を更新することができます。 (登録料と同様に更新手続でも5年分の分納が可能です)
